| 音楽サロン表紙 | 総目次 | ロマン派目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |
わが指針 |
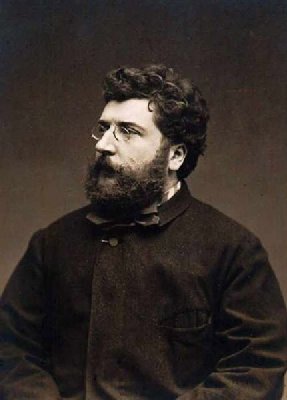 |
|
作品名 |
作曲年 | 初演年と場所 |
|
医者の家 オペラ・コミック |
不明 |
楽譜不明 |
|
ミラクル博士 オペレッタ |
1856-57 |
1857 パリ、ブフ・パリジャン劇場 |
|
ドン・プロコピオ オペラ・ブッファ、イタリア語 |
1858-59 |
1906 モンテ・カルロ |
|
真珠とり オペラ |
1863 |
1863 パリ 、リリック座 |
|
美しきパースの娘 オペラ・コミック |
1866 |
1867 パリ、テアトル・リリック |
|
マルブルクは出征する オペレッタ |
1867 |
1867 パリ 破棄? |
|
ノエ:アレヴィの未完のオペラを補筆 |
1868-69 |
1885 カールスルーエ |
|
ジャミレー オペラ・コミック |
1871 |
1872 パリ、オペラ・コミック劇場 |
|
ソルーシーレーピフーパン オペレッタ |
1872 |
1872 パリ、破棄? |
|
カルメン オペラ・コミック |
1873-74 |
1875 パリ、オペラ・コミック劇場 |
<原作者プロスペル・メリメ>
小説「カルメン」(フランス語)の作者プロスペル・メリメProsper Merimeeフランス(1803-70)の父は画家また化学者でもあり、母は絵をよくした。メリメは早くから芸術に興味をもち、パリ大学では法律を学んだが、まもなく文学に魅せられていった。ユゴーらの保守的ロマン派に対抗し、スタンダールらとともに自由主義的な一派を形成した。博学多才、多くの欧米語に通じ、ギリシャ、古ラテン文学や美術、考古学にも造詣が深く、晩年にはロシア近代文学の翻訳もしている。博学を誇り、人を煙に巻くのが好きだった。例えば架空の作者の名をあげ、自作なのに翻訳ものとして発表したりという風に異才ぶりと個性を発揮した。ex.「クララ・ガスルの戯曲集」(1825年)、「ギュスラ」(1827年)などがある。
メリメの小説は主に中編もので、1830年を中心にしてその前後10数年間に書かれた。「シャルル九世年代記」、「タマンゴ」、「マテオ・ファルコネ」、「エトリュスクの壷」、「コロンバ」、「カルメン」3)などである。1841年、歴史記念物監督官に任じられた。そのためかメリメは歴史研究に関心をそそいだ。1843年には歴史アカデミー会員に、翌年にはアカデミー・フランセーズの会員に選ばれている。いずれもフランスにおける学術界および文学界の最高の栄誉である。フランス皇帝ナポレオンⅢ皇后になるウージェーニーとは20数年前から友情を交していた。彼女が皇后になったのを機にメリメは保守派に転じてしまう。さらに1853年、上院議員に挙げられ、その後は皇室の側近者(ナポレオンⅢの廷臣)として、政界や社交界に権勢をふるった。
小説「カルメン」は、1845年10月1日号の「両世界評論」誌(月2回刊)に発表された。スペインを舞台にしているこの小説は、メリメの2回にわたるスペイン旅行の所産である。マドリードで、モンチホ伯爵夫人(後のナポレオンⅢ皇后ウージェーニー)の口から直接聞いた侠賊の実話を基にしている。異常な人物や出来事好みのメリメは、このスキャンダラス事件を洒脱な文体、歴史と考古学の目で投影された的確な表現で対し、終止冷静な態度を崩していない。今でいえば三面記事やテレビのワイドショーにでも登場するようなスキャンダラスな題材でもあるが、非常に斬新な文学様式で構成されている。
ロマ民族という流浪民族の血をひく娼婦カルメンの実話を題材している。単なる悲劇とは一線を画するものであろう。エスニックな世界、異形と任侠的世界にいわば傍観者のような視点が注がれている。「カルメン」はメリメの代表作であり、メリメ文学の特徴はこの一編に凝縮されている、といってよいだろう。
メリメがロシア文学のフランスへの移入紹介に力を入れるのは、 文学生活の終りの頃であった。フランスでほとんど知られていなかったプーシキン、ゴーゴリ、ツルゲーネフ等、ロシア作家の作品をいち早く翻訳し、紹介している。
[注]
3) メリメ(堀口大学)/カルメン/新潮文庫
<流浪の民・ロマ民族>
従来一般的に使われてきたジプシーGypsy英語は、現在、差別語として認識されている。そのため現在はジプシーを排してロマroma(romの複数形)が用いられている。これは彼ら自身が自称として使っている語である。この民族を指していう語はたいへん多い。差別語とは単純にはいい切れない語もある。この民族を指す語として世界各国で違った語が存在し、あげれば枚挙の暇がない。また音楽作品名として用いられたロマを示す語も多い。サラサーテ「ツゴイーネル・ワイゼンZigeunerweisen」(ドイツ語、<ロマ風>の意)、シューマン「流浪の旅Zigeunerlebenツゴイネルレーベン」(ドイツ語、<ロマの生活ぶり>の意)。またリスト「ハンガリー狂詩曲」やブラームス「ハンガリー舞曲」は、明らかにロマ音楽を意味し想定されている。西欧人の東欧に対する偏見もあってハンガリー音楽=ロマ音楽というような極端なコンセプトがあったことを示すものである。たしかにそれらの地にロマ人が多く住んでいたし、ロマ音楽の影響も多く受けてもいた。
そうそう、もう一つある! これも使用不可になるのだろうか?! 自由奔放に生きる人々のことをボヘミアン(放浪者?)という。これもボヘミヤ(現チェコ)=ロマというような誤った飛躍があってのことだった。東欧にロマ民族が多くいたからであろう。以上のようにハンガリーやチェコの人に対しても、問題点を有していることを忘れてはならないだろう。
スペイン語ではヒターノgitanoという。古今のスペインの詩文や祈祷文に独特の神秘とファンタジーをこの語に込めて用いられてきた。自らを卑しめて謙虚さを表して、ヒターノと呼ぶのである。神の前で自らを謙虚さを表したり、神に祈る者自身を指している用例が多い。すべての人間は神の前では小さな者であり、不完全で罪人であるという考えから、自らを卑しめてロムrom=ヒターノと言う大まじめな表現がたいへん多く見られる。たしかにこれは差別も悪意も存在しない。とはいえ広い意味で他者への軽蔑を含む面もあって、さらに自虐的な匂いも否めない。ヒターノgitanoは、厳密にはロマ民族を指すことも確かである。
ロマ民族は今日、黒アフリカ、東南アジア、中国、日本を除いてほとんどの国々に存在しているといわれている。総人口は推定で800万人以上とされる。ロマ民族は6世紀から7世紀にかけてインド北西部から移動を開始したと考えられており、その原因は不明とされている。14世紀になって東部ヨーロッパやバルカン半島に移ってきた。Gypsy英語という名はEgiptian(エジプト人)に由来するともいわれる。たしかに頭のEをとって発音するとジプシーに似ており、エジプトから来た人々と思い違いしたことも考えられる。とするとエジプトに対してもたいへん失礼なことになる。
ロマの人々は現在でも定住を好まず――ヨーロッパ各国で定住地を提供する申し出があっても、人目につかず独特のライフスタイルをして暮している。イタリアやスペインのような西ヨーロッパの観光地では一部のロマの人たちによる盗みや掠奪行為があったり、観光者の恐怖の対象ともなっている。概ね東ヨーロッパなどではそのようなことは見られないようである。現在、キャンピングカーを連ね、共同的な移動生活を送っている人たちが多く見られる。たしかに2000年以前は、ロマの女性たちが髪にいわばカルメン風に、花を一輪挿したり、ロングスカートを着用していたことが多かった。。
<台本>
台本はリュドヴィク・アレヴィPLudovic Halevy(1834-1908)とアンリ・メイヤックHenri Meilhac(1831-97)とメイヤック(1831-97)が共同で書いた。原作と同じくフランス語である。原作とオペラの台本の間には、人物設定に多くの相違点をもっている。登場人物の名前の違いを別にしても、原作に出てくるカルメンの片目の情夫はオペラには登場しない。逆にオペラではホセの許嫁で名前まで与えられているミカエラは、原作では単に回想の中で出てくるだけで名前も与えられていない。
カルメンにいたってはさらに性格付けが異なる。原作と同じくオペラでもいささかあばずれではあるが、緩和されていて、たいへん生命感あふれるロマの女性として描かれている。それは自立する自由な人間像でもある。それはヴェリスモ・オペラの先駆としてふさわしい性格付けであったといえる。
原作では明らかに娼婦で、連込む男たちから持物をかすめ盗るような悪女として描かれている。彼女は片目の密輸人の情夫をもっている。北スペインのナバラ出身の生まじめなドン・ホセが、この亭主を殺すことになる。ホセは元神学生で、学生時代にスポーツ競技で友人をあやめてしまったという暗い過去をもつ衛兵として描かれている。カルメンのロマ女性の不気味さが強調され、それゆえの悪魔扱いにされる自由で情熱の女として描かれている。ホセがカルメンを殺害する場所は、原作では山中の洞窟、オペラでは闘牛場の前としている。
ナバラ出身のミカエラの登場は台本での創作で、カルメンとは対照的な女性として描かれ、舞台では活躍する役柄である。そしてミカエラはホセの故郷で決められていた許嫁。彼を愛し、ホセも愛していたが、カルメンに一瞬に心を向け替えられてしまった。ほんの一時的にカルメンはホセに心を向けた。だがすぐ闘牛士エスカミーリョを愛し、エスカミーリョもつかの間の愛をカルメンと結ぶ。このようなボタンのかけ違いのような図式が、悲劇を生んでいく。このホセの人物像は、オペラのヒーローの従来のカテゴリーに属していない。カルメンと出会い、すぐカルメンから拒否される男である。ホセはカルメンを刺し殺すことによって、カルメンとの破滅的な愛を選んでしまったのである。
<作曲の経緯>
1873年から1874年にかけて作曲された。ビゼーは色々なオペラのスタイルを手本にしている。自分の他の作品からも借用している。合唱、管弦楽部分の多くは、特色あるオペレッタの様式がみられる。スペイン風のエスニック要素が見られるものの、純スペイン風ではなく完璧にフランス風オペラといってよいだろう。それは要を得た各場面の音楽表現で明瞭である。禁欲的ともみえる切りつめた表現、そしてあふれるような生気とリズム、それに対してこの上なく冷静、客観的である。ここから不思議に心に迫る官能が一つとなって湧出ている。これはフランス的精神の産物であろう。「カルメン」のオペラの作りは、台詞がふくまれるオペラ・コミックとし、番号オペラの形を取っている。根本的にヴァーグナー4)とは異なる。
それと各幕の前に演奏される第1幕の「前奏曲」と第2幕、第3幕、第4幕の前に演奏される「間奏曲」はどれも秀悦そのもので聴く者をとらえて放さない。独立して演奏会の曲目ともなっている。特に「前奏曲」は圧巻そのもの。
ビゼーの死後、「カルメン」は台詞が含まれるオペラ・コミックの形ではなく、台詞はすべてレチタティーヴォで歌われる完全なオペラ形態で上演されたのであった。それは台詞が含まれるオペラ・コミックをオペラより一段低く解釈する風潮が当時からあり、20世紀後半までその様な見解は続いていた。そのためか1875年5月にビゼーにレティタティーヴォ化する作業を、ヴィーン宮廷歌劇場のディレクターが勧め、ビゼーと契約を結んでいた。たが、6月1日にビゼーは死去、パリ音楽院時代の友人ギロー5)によって、台詞をレチタティーヴォ化する補作版が作られた。1875年10月23日ヴィーン上演からこれが一般的に20世紀中頃まで用いられていたのであった。
だが、ビゼー生前中より台詞が含まれるオペラ・コミックの原典版「カルメン」は高く評価されていたことも事実である。20世紀後半からビゼーの原典版=オペラ・コミック版「カルメン」についての評価がより高くなり、現在ではギローの補作版は、上演されることは全く無くなったのである。
タイトル・ロールはメッゾ・ソプラノ、台本の副産物であったミカエラにソプラノを当てているのも興味深い点である。これは後のオペラにも大きな影響を与えた。
[注]
4) ヴァーグナーWagnerドイツ(1813-83):過去のオペラのあり方を否定的に考え、総合芸術としての概念の楽劇Musikdramaを打立てる。音楽よりドラマが重要とし、示道動機Leitmotivによって人物、概念、感情などを示していくやり方。
5) ギローGuiraudフランス(1837-92):1859年ローマ大賞を得る。76年以後パリ音楽院で作曲らを教え、デュカース、ドビュッシーらの優れた弟子を育てた。ビゼーの原曲から「アルルの女・第二組曲」、「カルメン組曲」を作曲者の死後に編曲した。あとオッフェンバックの唯一のオペラ「ホフマン物語」のオーケストレーション=管弦楽化を担当した。
<オペラ「カルメン」の受容>
初演は1875年3月3日、パリのオペラ・コミック劇場で行われた。大成功とはいえないが、失敗でもなかった。ビゼーの死後の1875年6月3日(6月1日ビゼー死去)にも上演は行われたが、3ヶ月で23回目の上演ということになる。これは上演回数の著しい多さを示しすものであった。
不評の多くの理由は音楽にあるのではなく、従来のオペラの題材と筋書きとは全く異なり、その不道徳性にあった。それに加えカルメンを演じたガリ=マリエはオペラ歌手というより女優で、大変あけっぴろげで非常にどぎつい演技をしたということである。サロン的で優雅な雰囲気が漂うオペラ・コミック劇場には適合しなかった。公的オペラ界のお偉方すべてを震え上がらせたという。ダーティな題材が強調されてしまったようであった。
ヴァーグナーに嫌気をさしていたニーチェ6)は、「カルメン」こそヨーロッパ芸術の地中海化への原理にほどよくかなった理想的オペラとしている。これは当を得た評価といえる。だが、当時の批評家たちは旋律に乏しく、明確な輪郭に欠け、重苦しいオーケストレーションのために押しつぶされているとした。批評家たち言葉は全く当たっていない。当時の批評家好みでなかったのか、いや彼らには正しく評価ができなかった、と思われる。
そうした1875年10月23日、ギローのレチタティーヴォによるドイツ語版がヴィーンで初演された。これが、世界的成功の突破口を開くこととなった。1876年にはブリュッセル、アントワープ、ブタペスト(ハンガリー語版)と上演されていった。1878年ペテルブルグ(イタリア語版、チャイコフスキーも観て、「カルメン」は10年後には絶対に世界一人気あるオペラとなる、といっている)、ストックホルム(スウェーデン語版)、ロンドン(イタリア語版)、ダブリン、ニューヨーク(イタリア語版)、フィラデルフィアで上演‥‥‥という風に異例の人気の伸びを示した7)。そして「カルメン」は数々のスター歌手も生み出す機縁になるオペラであった。
オペラ「カルメン」は1875年にヴォーカル・スコア、1880年にはオーケストラ・スコアが出版されている。1886年にはドイツ語版、同じくドイツ語版とイタリア語版が合本が出版された。他はイタリア語版のもの、イタリア語版とフランス語版の合本もある。1895年には英語とフランス語のものも出された。いかに加速的に人気が上昇したかが分かるのである。1964年にカッセルのアルコーア社によって(校訂はフリップ・エーザー)初演時の原典版が出版された。これが原曲のオペラ・コミックに戻そうという転換点の始りになった。ドイツ語訳と英語訳が合わせて載せられている。
日本での上演は1919年ロシア歌劇団(イタリア語版)により横浜で初演、1922年には日本人の手によって初演された。
魅力あふれる「カルメン」の音楽、様々な編曲やアトラクティヴな楽曲を生むことになる。ギローによる「カルメン組曲第1番、第2番」(管弦楽曲)、サラサーテの「カルメン幻想曲」(ヴァイオリン独奏と管弦楽)などと多種多様な作品が生まれていった。そして20世紀には様々なオペラ映画「カルメン」も多数作られてきた。
[注]
6) ニーチェNitzscheドイツ(1844-1900):初めはヴァーグナーを支持していたが、1878年代にはヴァーグナーから離れていく。1888年5月に出した反ヴァーグナーの著作「ヴァーグナーの場合」に示された。
7) オペラやオペラコ・ミックなどすべてはわが国も含めて、その国の言語で上演されるのが一般的であった。わが少年時代に観たオペラはすべて日本語であった。イタリア・オペラグループが1956年に来日して上演した時はイタリア語だったのを憶えている。
<響きのよい音楽と回心しない主人公>
ビゼー「カルメン」は、フランス国民オペラを樹立した記念碑的名作といえるだろう。またオペラ史においても高い評価を得ている。さらに魅力ある娯楽性と高い音楽性の両面をもっている希有な芸術作品である。舞台を観ないでも響きのよい音に驚くより他はない。しかもその華麗な音楽は軽薄とすれすれにあるようにもみえ、我々を一瞬戸惑わせる。今なおこんなに愛されるオペラもめずらしいのではないだろうか。カルメンの音楽は、しばしば台本を越えた演出をすることがある。激しく過度な演出が施されることもあるが、ビゼーの音楽が勝ち、美しい調和を壊すことはないのが不思議である。。
題材から検証すると、例えばヴェルディの「椿姫」は回心する高級娼婦として描かれている。それに引き換え、カルメンは殺されても回心しないし、ホセの愛も受け入れない。オペラ「カルメン」にはカルメンと対照的な女性、子供の時から決められていた故郷の許嫁ミカエラが登場する。彼女は清純でしっかり者で、カルメンに騙されているホセを救い出そうとする良妻賢母型の女性。かろうじてこのオペラに教訓的要素を引出せる(?)唯一の登場人物であろうか。それでもすべてを越えて、自由奔放の破滅型のカルメンに理屈抜きに惹かれてしまうホセを描くための絶妙な登場人物であった。
自由な女性、カルメンの出現は、1871年のパリ・コミューン(パリ市民自治体)崩壊の流血事件と似ている。ビゼーも自宅の通りの側溝で屍の血を見た。このコミューン参加者、女性が活躍したコミューンのヒロイズム、つまり敗北の美学が「カルメン」に存在している。殺されるカルメンにビゼーは、コミューンの敗北をみていたのだろうか。たしかに彼が嫌悪していた政府軍が、コミューンを抹殺したのである。知らず知らずのうちに世の歴史や動きが芸術に反映反映したり、影響を与えることがある。オペラ「カルメン」はパリ・コミューンの産物だった、といえるのかもしれない。
<物語>
| 第1幕への前奏曲 |
| 第1幕 | 1830年頃のスペイン・セビリャのタバコ工場前広場 |
煙草工場に面した広場では衛兵=竜騎兵たちが、駐在している。そこへ田舎娘があらわれ、ホセは何処にいますかと尋ね、まだ来てないよ、といわれて立去る。それはホセの故郷の許嫁のミカエラであった。タバコ工場の休憩時間を告げる鐘が鳴り、女工たちが出て来た。町の男たちも女工たちの一人、カルメンを目当てにやって来た。そこへカルメンは大見得を切って登場する。彼女は純朴な衛兵ホセに興味をそそられ、手にした花をホセに投げつけ、工場内に走り去る。そこへミカエラが来て、母から預かって来た手紙とお金を渡す。母からだ、といって口づけをした。しばし二人の時間を過ごし、ミカエラは去って行く。
すると工場は大騒ぎになる。カルメンは一人の女工仲間と喧嘩を引き起こし、傷をつけてしまったという。衛兵たちにより鎮められ、カルメンは捕えられた。ホセはカルメンの見張りをするが、カルメンはホセを誘惑し、逃してくれたらバスティアの酒場で待っている、と告げた。ホセは彼女の誘いに応じて、二人は一芝居を打つことになった。その時、ホセはカルメンに突き飛され、その拍子に倒れ、カルメンは逃げてしまう。
| 第2幕への間奏曲 | アルカラの竜騎兵 |
| 第2幕 | リーリャス・バスティアの酒場 |
第1幕より約2ヶ月後。その間ホセはカルメンを取り逃がしたため、営倉入りになっていた。カルメンと約束していた酒場には、カルメンと密輸団仲間たちがいる。ホセの上司の龍騎兵隊長スニーガも来ていて、ホセが釈放された、と皆に告げる。そこへ闘牛士エスカミーリョがやって来る。彼はカルメンに目を付け、彼女をくどきにかかる。だがそれは間に合っているのでお生憎様、とばかりにカルメンは拒絶する。一行が去るとホセがやって来た。やっと営倉から出されたところだった。カルメンは色っぽくカスタネットの踊りで歓迎する。彼女は盛んに竜騎兵からの脱走をすすめ、密輸団一味に加われと誘惑する。ホセの上司の龍騎兵隊長スニーガ戻って来た。ホセを見て帰営しろと命令するが、ホセは拒むので二人は決闘となる。だが、密輸仲間たちによって、龍騎兵隊長スニーガは押さえられた。これでホセは、密輸団に仲間入りすることになってしまう。
| 第3幕への間奏曲 |
| 第3幕 | セビリャ近郊の山地 |
セビリャ近郊のシャラ・マドム山地。密輸団たちが荷物を背負ってやって来た。ホセは浮かない顔、カルメンはロマ占いをするが不吉な死としか出ない。カルメンはすでにホセをうとましく思い始めていた。そこへホセを連れ戻すために、なんと故郷ナバラからミカエラがやって来た。ミカエラは人影を感じて身を隠す。それはエスカミーリョであった。彼はカルメンにセビリャの闘牛の招待を申し出て去って行く。ミカエラが一味の前に現れ、ホセに対してホセの母が病気であるので一緒に帰ろう、とホセを説得する。だがホセは闘牛士の後を追おうとしているカルメンに嫉妬し、彼女に後ろ髪がひかれていた。ついにカルメンにバカにされながらも、ミカエラと共に母の所へ帰って行く。
| 第4幕への間奏曲 | アラゴーネ |
| 第4幕 | セビリャの闘牛場前 |
闘牛見物にやって来る人々で、闘牛場の前はいっぱいである。闘牛士たち、カルメンと彼女の女友達なども現れる。エスカミーリョも登場して、カルメンのために必ず勝つと宣言する。カルメンは、友達にホセが来ているようなので気をつけろ、と注意される。そこへホセが身をやつした姿であらわれ、カルメンに話合いを求める。二人は場外に出る。ホセは愛の復活を求め、カルメンは断固として受け入れない。おまけにカルメンはホセが与えた指輪を、投げ返すのであった。闘牛場からは歓声があがる。カルメンは場内に入ろうとする。ホセは阻み、所持していた短剣でカルメンを刺してしまう。と同時に場内で勝利の大歓声があがる。牛も刺し殺されてしまったのだ! ホセはただ呆然とその場に立ちつくして「俺を逮捕してくれ‥‥‥俺が殺した! おお、カルメン!
大切なカルメン!」 とむなしく叫ぶばかりであった。
| カルメン ドン・ホセ エスカミーリョ ミカエラ |
アグネス・バルツァ(Ms) ホセ・カレーラス(T) サミュエル・レイミー(Br)
レオーナ・ミッチェル(S) |
| カルメン ドン・ホセ エスカミーリョ ミカエラ |
ジュリア・ミゲネス・ジョンソン(Ms) プラシド・ドミンゴ(T) ルッジェロ・ライモンディ(Br) フェイス・エシャム(S) |
1997-2024
| 音楽サロン表紙 | 総目次 | ロマン派目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |
わが指針 |